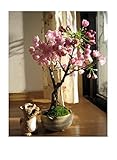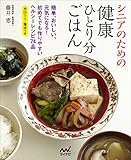詞書
藤原三善が六十賀によみける
この歌は ある人 在原時春かともいふ
鶴亀も
千歳ののちは
知らなくに
あかぬ心に
まかせはててむ
伝 在原滋春
(在原時春 作 との説もあり)
ことばがき
藤原三善が六十の賀(が)によみける
このうたは あるひと ありわらのときはる かともいふ
つるかめも
ちとせののちは
しらなくに
あかぬこころに
まかせはててむ
でん ありわらのしげはる
(ありわらのときはる さく とのせつもあり)
長生きと言われている鶴と亀も
千年先は知らないこと
でもあなた様の寿命は
たとえ千歳であっても飽きることはない私の心にまかせて
このお祝いの歌を
結ばせていただきます
九月十七日って敬老の日だったのですね。
あれれ?そうだっけ?
十七日って半端な感じがする・・・
って日曜日だから振替休日・・・?
ではないか、だってそれなら昨日が敬老の日になる・・・
などといかにも私らしく愚かなことを思い浮かべたら、
平成十五年(2003年)からは
九月の第三月曜日が敬老の日となっていたんです。
あははは、なーに今頃疑問に感じているんだよ・・・。
今年は平成三十年(2018年)だぞ!
何年たってるんだよ!
だって毎年の祝日とかに、
いちいちじっくり考えたりしないのだもの・・・。
祝日とは単なる祝日だよお・・・。
それでもってすぐに忘れる・・・
って何を考えているんでしょうね・・・。
ちなみに、ご存知でしょうが、
それまでの敬老の日は九月十五日だったのです。
ひょっとして、
彼岸の入りとかと間違えそうだったりするから変更した・・・
なんてことはあるわけないですよねえ。
だって、それほど日にちが離れていないもの。
要するに、ボーっとしているといろいろ変わってしまうと、
そういうことだったんです・・・。
あはははははははははははははははははははは・・・ ( ´艸`)・・・
・・・(´;ω;`)ウゥゥ・・・😢・・・
あまりにも今さらですが、うかうかしてはいられませんね。
・・・😓・・・😅・・・。
何でも、昭和二十六年(1951年)から
九月十五日を「としよりの日」と呼ぶことになり、
それが昭和三十九年(1964年)からは「老人の日」となり、
昭和四十一年(1966年)には「敬老の日」となって、
平成になったら、というより二十一世紀になったら、
九月の第三月曜日が敬老の日ということになりました。
としよりの日とか老人の日とか、
ネーミングに問題があったから敬老の日になったのだろうなあ、
やっぱり。
またまたちなみにですが、
あの聖徳太子が、
四天王寺に悲田院をおつくりになったと伝えられている日にちなんで、
九月十五日とされたようですね。
で、ようやく上の歌ですが、
何だか古語辞典とかで少し調べてみても、
今ひとつはっきりくっきりした「意味」というのが
つかみにくい・・・。
かなり古い和歌で、言葉が変えられてしまっていたり、
日本語そのものも変わっていて、
よくわからない歌となっているのかもしれない
と思ったりします。
とはいえ、鶴亀、千歳、
こんなおめでたい感じのする言葉が使われていて、
還暦まで生きることがおそらく今よりは難しかった時代の
還暦祝いの和歌ですから、
たぶん、たぶん、
おめでたくて良いお歌・・・です。よね・・・?。
そして、またまたまた ちなみにですが、
藤原三善さんとはどなたかというと、
・・・よくわからないみたいです。
あっ、在原滋春さんは、
かの有名な(?)在原業平さんの御次男で、
それから在原時春さんとは、
この在原滋春さんの御長男らしいですね。
つまりは、昔々のことを詠んだ和歌なのだなあ・・・。
それこそ千歳を経ている・・・。
などとつらつらと書き連ねていたら、
敬老の日はすでに暮れて行ってしまうのでした・・・。
記念の日だの
まあ
いろいろと言われているけれど
人によって
とらえ方は
いろいろですよね