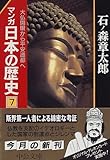この歌はある人 ならの帝の御歌なりとなむ申す
竜田川
もみぢ乱れて
流るめり
渡らば錦
なかや絶えなむ
伝 奈良帝(ならのみかど のちの平城天皇へいぜいてんのう)
このうたはある人 ならのみかどの おほんうたなり となむまうす
たつたがわ
もみぢみだれて
ながるめり
わたらばにしき
なかやたえなむ
でん ならのみかど のちの へいぜいてんのう
この歌はある人によれば ならの帝の御製であろうと言う
竜田川には 色とりどりの もみじ葉が 入り交じっていて乱れ流れている様子だ
川を渡ってしまえば その錦の流れは 流れのなかばで途絶えてしまうであろう
ぼやぼやしているうちに(?)もうすっかり紅葉の季節となりました。
早いですねえ・・・。
そんなことを呟いている間にも、ときは過ぎ去って行ってしまいます。
なんだか・・・涙が・・・😢・・・こぼれそう・・・。
駄目ですね。
こんなことでは。
少しはしゃっきっとしなければなりません。
そうです。
人からしゃんとしているように見えるかどうかは別です。
だけれども心は一応、
そう、少しはしゃんとする、ということで。
なので、まあまあ、とりあえず、少しは気を入れてぼちぼち行きます。
上の歌は、細かいことなどはっきりしないものの、
奈良帝(ならのみかど)との通称でも知られる
平城天皇(へいぜいてんのう)が詠まれたとも伝わる御歌です。
歌集によっては、
文武天皇御製、
あるいは聖武天皇御製とも記されているそうです。
平城天皇は第五十一代天皇、
桓武天皇と皇后藤原乙牟漏(ふじわらのおとむろ)との間の第一皇子でもあります。
すでに中臣(なかとみ)氏改め藤原氏が、
しっかりと中枢(?)に入っていたのですね・・・。
平城天皇の名前は最初は小殿(おて)、後に安殿(あて)と改名します。
「おて」ではワンちゃんに「お手」みたいで、
今ひとつ聞こえが良くなかったからでしょうか。
その当時お手はなかったかな・・・。
それとも、第一皇子だし、どうせなら小さな殿(との でん)よりは、
安心安全安寧な殿のほうが良い、
というようなことでもあったんでしょうか?
ですけれども、とにかく安殿親王殿下、
のちの平城天皇陛下、ということですね。
何でも、生まれつきの風病病みという体質だったと言われています。
風病病みというのは、
現在ではあまり使われなくなった印象なのですが、
ノイローゼの一種だと説明してあるものを読んだりしました。
ということはおそらくですが、
神経過敏で精神と体のバランスを崩しやすい、
というような症状だったのではないでしょうか。
繊細なところがあり、気難しくもあったということなんでしょう。
それで肝心の安殿親王のちの平城天皇と聞いて何を思い浮かべるかといえば・・・
何にも思い浮かばない・・・
あれ?これは何かがおかしい・・・
桓武天皇の皇子・・・
桓武帝は何だかよく知りませんが大きな仏様が好きだったような気が・・・
そんなことを思ってから三日くらいたって何が変なのかようやく気がつきました。
そう、桓武天皇は桓武天皇で、聖武天皇ではなかったのです。
当たり前ですね。
まあ「む」だけは合っているので、半分くらいは正解(?)ということで。
それにどっちにしろ親戚か、親戚みたいなものなのだし・・・。
(別人ですが。)
むかーし昔、
漫画だかイラストだかで読むことができる日本の歴史だとかなんとかで、
大仏の作り方だとかを解説していたことを思い出しました・・・。
それはともかく、安殿親王のちの平城天皇です。
この方といえば悲劇の早良親王をなぜか思い浮かべてしまいます。
早良親王の怨霊によって安殿親王のちの平城天皇が発病したという風評は、
生まれつきの体質もあったようですからかなり微妙ではあります。
それでも症状の悪化というものもあるので何とも言えません。
それとも別の病気までが加わってしまったのでしょうか。
ただ、どうなんでしょうか。
早良親王にとっての一番の恨みの標的(?)って
安殿親王のちの平城天皇だったのでしょうか。
どうもそういうわけではなかったのではないか、
と思います。
早良親王が皇太子になれずにそのかわり皇太子になれたのが安殿親王、
そしてさほど邪魔されず(?)天皇に即位できたので、
何となくイメージで一番恨まれているかのような印象はあるのかもしれませんが。
でも、どうも早良親王の怨霊(?)の最初の頃の犠牲者(?)は、
贈皇太后で桓武帝と早良親王の母である高野新笠(たかののにいがさ)や、
桓武帝の皇后で安殿親王の母でもある藤原乙牟漏(ふじわらのおとむろ)など、
だったらしいです・・・。
他にも、いかにも怨霊のしわざらしく(?)悪疫が流行するなどして、
それだけが原因かどうかはともかく皇族や藤原氏などの貴族からも死者が続出、
当然庶民の犠牲もあったことでしょう。
今ではどんなものか明確にはわかりませんが災害も続いたようです。
これらが本当に起こったことならば、
安殿親王のちの平城天皇が一番の標的だったとは言い切れません。
でもとにかくそういった様々な災いは、
早良親王の怨霊の恨みから起こったことと考えられたのですね。
そんなわけですので、
早良親王はその後の平安時代の超有名な(?)怨霊たちよりは、
失礼ながら何となく格落ち(?)の感がないこともないのですが、
それでも立派な(?)怨霊伝説の持ち主とは言えそうです。
さすが奈良時代のお方、より古いだけに、何やらおどろおどろしさにも
後の時代とは違いがあるような気がします。
早良親王は、
天智天皇の孫であり志貴皇子(しきのみこ 施基、志紀などとも)の
第六王子にもあたる光仁天皇(こうにんてんのう)の第二皇子で、
桓武天皇の同母弟と言われています。
出家していたらしいのですが、
光仁天皇の即位で親王に、
そして兄である山部親王が桓武天皇となることで皇太子となります。
ですが、すでにここらあたりから、
きな臭い問題の芽(?)が生まれてきてしまったような・・・
桓武帝は前の時代の奈良仏教的な政治の弊害を何とか刷新するため、
僧らの不法には厳しくあたり、
最澄や空海を起用するなど新たな仏教の興隆に努め、
また律令を改良したり地方政治にも力を注いだ、と今に伝わります。
そして何といってもよく知られているのが遷都ですね。
長岡京造営をしていたのに、わずか十年ほどで平安京遷都が行われています。
長岡京というのは、実は規模が大きく、立派な都を目指していたそうですね。
それが平安京に・・・遷都、
このあたりにも早良親王の怨霊の祟り・・・
などと長い間言われてきた理由がありそうです。
早良親王は長岡京造営の中心人物のひとりであった藤原種継(ふじわらのたねつぐ)
が暗殺されるという事件に連座して皇太子を廃されて
乙訓寺(おとくにでら)というところに閉じ込められ、
その後は淡路に配流されることになります。
その淡路に流される際におそらく無実を訴える意味で抗議の断食を行い、
淡路に着く前に亡くなってしまいました。
後味が悪いことこの上ないこの事件ですが、
なんとも怪しげな話があり、藤原種継の暗殺事件を利用して、
早良親王にかえて桓武帝の皇子である安殿親王を皇太子につけたい思惑があった
桓武帝とその周辺が仕組んだのではないか、とも言われているようです。
これは古代における、なんというかあれですよね、
部族社会、氏族社会、血族社会のなかでの下剋上(?)みたいな感じ、
とも言えないでしょうか。
時代が古いと、皇族や貴族とはいっても・・・
やる気に満ち満ちていて、野心もあり、
情熱ある冒険家がたくさんいたようですね。
これって「雅(みやび)」の正反対だと思います。
それでもって、まあいろいろ、いろいろとあって長岡京のほうはあきらめ(?)、
結局は平安京遷都ということになりました・・・。
歴史の方向が違っていたら、
京の都は今とは位置が違っていたのかもしれません。
そんなわけで様々なことがあったのですが、
安殿親王は皇太子になって、
およそ二十五年在位した桓武天皇のあとで、
平城天皇に即位します。
在位中には、
桓武帝が推進した(と言っていいんでしょう)、
都の造営だの征夷だの何だのかんだので疲弊していた国や民のため、
財政問題の解決に努め、官司(かんし)の整理や、
観察使を派遣して平安京遷都ののちの地方視察を行わせるなど、
政治と経済の再構築に積極的に取り組みました。
が、在位わずか三年ほどで持病の悪化を理由として、
弟である神野親王(かみのしんのう)のちの嵯峨天皇に
譲位してしまうこととなります。
その後、旧都である平城京に移り住んだことから、
奈良帝という通称で呼ばれることになりました。
それからがまたまた新たな(?)ドラマのはじまりはじまり・・・
ということで・・・
歴史の登場人物たちは、当然皆様とにかくいろいろあります。
だからこそ歴史のなかの主役(?)になれたのですね・・・。
それにしても長岡京だって大規模な造営を行っていたらしいので、
本当は住めないこともなかったのでは、などとも思うのですが、
やっぱり早良親王の怨霊の祟りが怖くて近づかなかったのでしょうか。
十年程度といっても造営は行っていたのだから
何だかとてももったいない・・・
こんな風に感じるのは
ドがいくつもいくつもつく庶民だからでしょうか・・・
ところで平城天皇のドラマチックな人生行路には、
藤原薬子(ふじわらのくすこ)という強い強い(?)女性の存在が欠かせません。
ここでも藤原氏ですね。
結婚したから苗字(?)が変わるという習慣は、
この頃はまだなさそうです。
妙な表現ですが、
藤原氏一族には何系統(?)の血族集団が
いくつくらい存在したのでしょうか。
さすが古代の人たち、生命力に溢れていてある意味では羨ましいです・・・。
人類はみんなきょうだいを文字通り体現しています。
そんなところもはっきりと古代人ですね。
藤原薬子という女性は、
平城天皇の東宮(皇太子)時代のときの妃のうちのひとりの「母」です。
娘が妃に選ばれたんですね。
妃の母という立場で後宮にも出入りが許されていたでしょうから、
それを利用してというか、何というのか、
どうも必要以上に東宮と仲良くなってしまった・・・
少なくともそういう噂にはなった、ということのようですね。
一度は後宮から離れさせられたようですが、
平城天皇が即位すると返り咲き、尚侍(ないしのかみ)にもなります。
これは出世したと言ってもいいのでしょう。
尚侍はけっこうな重職のはずです。
薬子の夫は藤原縄主(ふじわらのただぬし)、参議でもありました。
やはり藤原、藤原恐るべしですね。
思わず「なわぬし」と読んでしまい、いろいろ象徴的な名前、
などとも思いましたが「ただぬし」と読むようです。
昔の人なので記録は多くないようですが、
まじめな人で恩義にも厚い人、人から慕われる人柄だったと
記されているそうです。
薬子とはもともとあんまり仲が良くなかったのかもしれませんね。
勝手な想像ですが・・・。
それで藤原薬子といったら、ここでようやく(?)
「薬子の変」ですね。
病を理由に皇太弟であった嵯峨天皇に譲位、
平城天皇は平城上皇となります。
平安京から旧都平城京の旧平城宮に移ったので
健康を少し取り戻してやる気が出たのか、
薬子とその兄、藤原仲成(ふじわらのなかなり)の計略に
まんまと引っかかったのかはよくわかりませんが
(仲成は薬子のおかげでか参議になったこともあるようです)、
結局は二重の権力の場が存在することになり、
ふたつの朝廷が存在するような形で、
上皇と天皇とが対立してしまうことになります。
再び平城京を都とすることを官人や貴族たちなどに呼びかけたりするものの、
嵯峨天皇のほうが上手だったらしくうまくいかず、
なんと東国への逃亡を図って失敗、捕らえられ平城京へ連れ戻され、
出家しました。
藤原薬子は毒薬で自害、
その前に兄の仲成は矢で射殺されたそうです。
これがいわゆる「薬子の変」ですよね。
ここまでの平城天皇の運命の変転を眺めてみると、
早良親王の怨霊の影響もあると言えばありそうですが、
さらに怨念のパワーがありそうな
薬子の恨みまでかっていそうです・・・。
あるいは早良親王の怨霊の怨念は、
身内であった皇族と藤原氏にしっかり向けられたと考えれば、
恨みは見事に結実(?)したとも言えます。
なのですが・・・
平城上皇のほうは一応は罪人扱いではあったのでしょうが、
それなりに厚遇されていたようで、
その頃としては天寿を全うしたともいえる年齢で没しています。
早良親王は薬子の変に遡ること十年前に
崇道天皇(すどうてんのう)と追号され、
淡路に葬られていたのを大和に移葬されました。
それだけ祟りが怖かったということですね。
ですけれども薬子の変は起こってしまいました。
とはいえ元平城上皇は、あくまでその時代としてはですが、
標準的な(?)年齢くらいでこの世を去っています。
これでは、怨霊の祟りは完成(?)していないようにも感じられます。
それはもちろん事件後の元平城上皇は、
楽しく毎日を過ごすというようなわけにはいかなかったでしょうが。
早良親王の怨霊は、
恨みのかたまりとなっても意識の底は皇族、
ですから当然一番の恨みの標的は、
皇室に取り入りある意味乗っ取って
権力をほしいままにしようとする存在、
それがやはり藤原氏であった、
と言ってそれほど間違ってはいないと思います。
それにしても、古代の皇族や貴族は、
かなり直接的な方法で権力を掌握しようとしています。
時代が下って雅やかな時代になると、
間接的な要するにより陰険な権力争いになる印象ですよね。
どちらの時代のほうが一般人が暮らしやすかったのかはわかりません。
ただ、古代の皇族や貴族は皆、武人的だった気がします。
平城天皇が旧都平城京に向かった際にも、事件後にも、
当然つき従った人たちがいたでしょうしね。
少なくともこの時代では、
律令だか法律だかを守るのは下の者だけで良いのだ!と
権力者が居直って(?)特権を享受できたかといえば・・・
難しかったのではないか感じます。
なぜって、だって周囲がやる気に満ち満ちていますから。
(最上位のほうにいる人たちも、もちろん同じみたいですが・・・。)
上に立とうとするからには力を誇示し、負けたとしても
その結果を直接的に受け入れなければならない時代だったのでは
ないでしょうか。
うまく表現できませんが、
時代が下るにつれて
皇族貴族はより現代人の思い浮かべるような皇族貴族となり、
それが結果的には長く続いた皇族と貴族が日本を統治する世の中の
終わりのはじまりとなったのではないか、
などと思います。
どんなことにでも
きっと終わりがある
だからはじまりもある